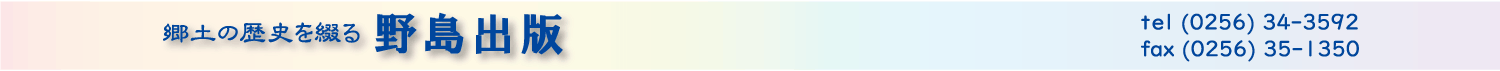燕市
燕市のおもな産業
伝統的工芸品 燕鎚起銅器
「わたしたちの新潟県」28,29ページ
鎚起とは「鎚」で「起」こすという意味で、おもに銅板を金鎚(ハンマー)でたたき,きたえ,形をととのえる技術です。
江戸時代に燕を中心とした地域に起こった産業で、1981年に伝統的工芸品の指定を受けました。
「鎚起銅器」ができるまで…
たたいて、のばして、形がつくられていきます。その工程を見てみましょう。
みごとな技ですね。この技術は江戸時代から受けつがれているそうです。
洋食器(スプーンやナイフやフォーク) (金属ハウスウェア)
「わたしたちの新潟県」27,34ページ
江戸時代の和くぎづくりから始まった燕の金属産業は、時代によって,やすり,鎚起銅器,きせるなど色々な製品を生み出してきました。
現代では,その伝統と技術を生かし,金属洋食器や,生活にかかせない色々な製品(金属ハウスウェア)などを製造しています。
洋食器をつくっている工場のようす
こういう機械でスプーンなどをつくっているんですね。
では,その燕の洋食器の製品を見てみましょう。
きれいですねー。技術の高さが分かりますね。